私は英語講師として英語を教える仕事をしています。
教える立場になって思うのは、コミュニケーション力の要る仕事だなということ。
でも実は私、それほどコミュニケーションが得意な方ではなかったんです。というかむしろ、苦手な方でした。
それでも今となっては、
「生徒さんの反応が以前よりもいい!」
と思うことが増えました。
もちろん私の教え方にはまだまだ改善点できることがあると思いますが、嬉しいことに生徒さんの中ではめきめきと英語の腕を上げている方もいます。
今回は、英語を教える仕事に興味がある方、実際にそういった仕事をしている方に向けて、私が2冊の本を通じて学んだ人を動かす心理について書きたいと思います。
教える仕事には、自ら能動的な姿勢で臨んでもらうための技術が必要
教える仕事では教える側の指導のしかたや知識が重要となってくるのはもちろんですが、一方で、
何かを効率よく学ぶためには本人のやる気や「できるかも」という自信が非常に重要
であると感じています。
これは、学ぶ対象に対する興味が不足していたり、
と思っていることは、なかなか頭に入ってこないとこれまで自分が英語を学んできた経験を通して分かっているからです。
このことについては、「英語学習のモチベーションが上がらない?独学でもやる気を保つ秘訣とは」という記事で、学ぶ側の立場としての実体験を書いています。
なので、教える立場として人にプラスの影響を与えるには、
相手に自ら能動的な姿勢で臨んでもらえるような働きかけが重要
です。これはつまるところ、コミュニケーション力ですね。
冒頭でも書きましたが、私はどちらかというとコミュニケーションが苦手なタイプでした。
今でも何気ない雑談や大きな飲み会なんかは苦手ですし、昔から女子が連れ添ってお手洗いに行くこと等が理解できない類の人間でした。なんというか、適当に群れることができないというか…
しかし自ら望んだとは言え、教える仕事を始めたことで、今まで以上にコミュニケーション力が問われることになりました。
効果的に教えるというのは、知識を伝達するだけでは不十分。
教えられる側の知識を吸収する姿勢が受動的なのと能動的なのとでは目に見えて結果が違ってきます。
講師としては、せっかくためになることを教えてもその人のためにならならいと意味がありません。
つまり、
いかに相手のやる気を引き出すか
が重要となってきます。
もちろん、本来であれば自然に習得したコミュニケーション力を発揮できれば良いのですが、まあそれはできるタイプなら苦労しないよねと(笑)
私のようにコミュニケーション力の不足を自覚している人間は、ちょっとした知識やテクニックを身に着ける必要があります。
そこで、人を動かす心理について改めて学んでみることにしました。実際に手に取ったのはこの2冊の本です。
- D・カーネギー著『人を動かす』
- Daigo著『一瞬でYESを引き出す心理戦略。』
D・カーネギー著『人を動かす』は、英語を教える仕事に応用できるコツが盛りだくさん!
こちらは世界的なベストセラー本で、タイトルの通り「人を動かす」ために知っておくべきことが書かれています。
「人を動かす」と言うと何やら大層な響きですが、原題は
です。
原題の方が分かりやすいですね。
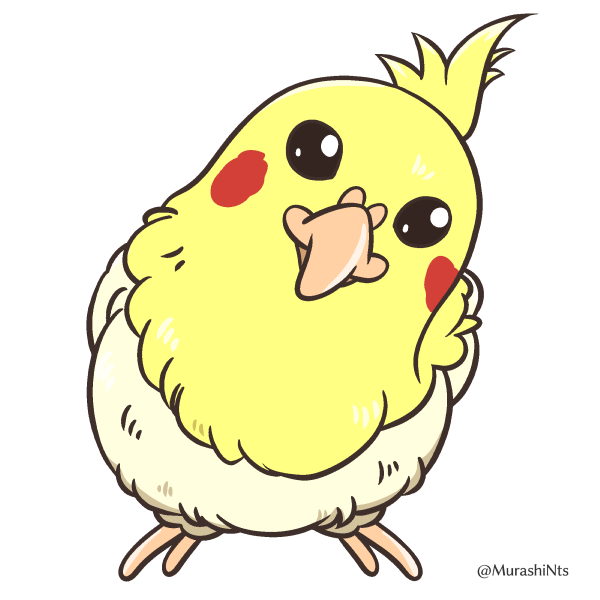
要は、人間関係のハウツー本という感じ。
『人を動かす』では、次の4つのタイプの人間関係についての原則について書かれています。
- 人を動かす三原則
- 人に好かれる六原則
- 人を説得する十二原則
- 人を変える九原則
この中で紹介されていることのうち、実際に生徒さんの英語学習に対するやる気を引き出す上で効果があったと思うものをピックアップしたいと思います。
名前を覚える
まず印象に残ったのは、人に好かれる六原則のうちの1つ、「名前を覚える」です。
人の名前を覚えるのが大事というのは当たり前のように思えますが、実際のところ毎日対応する相手が変わっていると、瞬時に一人ひとりの名前を正確に思い出すのが難しいときがあります。
しかも名前を覚えても、「間違えたら失礼だし…」とか、なぜかどぎまぎしてしまってなかなか人の名前を呼べないなんてことも…。
でも考えてみると、「あの人コミュニケーション得意だな」って感じる人って自然に人の名前を呼んでいるんですよね。
呼びかけるときに「すみません」といった言葉だけじゃなく、ちゃんとその人の名前を呼んでいます。
本書では、人の名前を覚えることを重要視し、一見重要でない立場の人の名前まで覚えていたという米国元大統領、フランクリン・ルーズベルトの話を引き合いに出しながら、このように述べています。
フランクリン・ルーズヴェルトは、人に好かれるいちばん簡単で、わかりきった、しかもいちばん大切な方法は、相手の名前を覚え、相手に重要感を持たせることだということを知っていたのである。ところで、それを知っている人が、世のなかに何人いるだろうか?
名前は、当人にとって、もっとも快い、もっともたいせつなひびきを持つことばであることを忘れない。
D・カーネギー著『人を動かす』より抜粋
誰かが自分の名前を覚えてくれていると、普通はちょっと嬉しく感じますよね。たくさんの人の中の一人ではなくて、個として見られている感じがするからです。
このことを意識してからは、一度に複数に教えているときでも、積極的に一人ひとりの名前を呼んでいくようにしました。
すると、徐々に心を開いてくれ、以前より熱心に英語学習に励んでくれるようになったんです。
名前を覚える、名前を呼ぶというのは些細なことのように思われますが、「人を動かす」上での効果は大きいということですね。
激励する
もう1つ本書の内容で印象的だったのは、人を変える九原則に登場する「激励する」という箇所です。
ここでの原則は
激励して、能力に自信を持たせる。
こと。
先ほども少し触れましたが、
「自分にもできるかも」という感覚が不足していたり、自分事として捉えていないと、なかなか知識や技術を習得することができません。
そもそも教えを求める立場の人は、その分野に明るくない人か、苦手だと感じている人なわけで、ただ解説されているだけでは内容が頭に入っていきにくいはずです。
実際に自分が教えを受ける立場で、なんとなく良かれと思って聞いた講演等で思い切りこくりこくりと舟をこいでしまった経験があるので分かります(笑)
本書では激励することに関して、このように書かれています。
子供や夫や従業員を、ばかだとか、能なしだとか、才能がないとかいってののしるのは、向上心の芽を摘み取ってしまうことになる。その逆を行くのだ。大いに元気づけて、やりさえすれば容易にやれると思い込ませ、そして、相手の能力をこちらは信じているのだと知らせてやるのだ。そうすれば相手は、自分の優秀さを示そうと懸命にがんばる。
D・カーネギー著『人を動かす』より抜粋
また、事故で頭を怪我し、学ぶ能力が低いとして特別学級に入れられていた子どもを変えた親の話が紹介されています。彼を変える取っ掛かりとして父親が息子に数学を教えている場面で、
正しい答えが出るたびに、大げさに喜んで見せる。とくに、はじめ答えられなかった問題を正しく答えたときは、大いにはやし立てた。…(中略)…記録が少しでも更新できると、彼はもう一回やりたがる。この子は、勉強が、やさしい、おもしろいものだというすばらしい発見をしたのである。
D・カーネギー著『人を動かす』より抜粋
とあります。この父親の熱心は働きがけが功を奏して、息子の成績は飛躍的に上がったそうです。
この話から分かるのは、学ぶ姿勢がその人の成長を左右するいうことです。
周りから「できない」と思われ、自分も「できない」と思っていると、伸びるものも伸びません。
なので教える立場の人は、
相手を激励することでその人の「自分にはできない」という考えを変える
必要があります。「自分にもできる」とか「学ぶのは面白い」と思ってもらえるように働きかけるということですね。
ちなみに、本書と同じ著者が書いた「人に話をきいてもらうための秘訣」についてのこちらの本もおすすめです。
Daigo著『一瞬でYESを引き出す心理戦略。』から、相手が本当に思っていることを知る術を学ぶ
こちらはメンタリストとして知られているDaigoの著書で、ビジネスパーソンが使える心理戦略について書かれています。
営業の仕事の人をメインにしているようですが、教える仕事をする上でも参考になる点が多くありました。
本書を読んで個人的に印象に残ったのは
- 観察する
- 無口な人ほど、実は話したがっている
という点です。
まずは相手を観察する。心の変化は目と口に表れる
「観察する」に関しては、
相手の心理状態を探るために何よりも大切なのが「観察する」ことです。
と書かれており、例として相手の表情に注目することが挙げられています。
興味があって面白いと思っているとき、目線は上下に動き、口は軽く開きがちになります。逆に興味がなくてつまらないと、目線は左右にふらふら動き、口は左右に固く閉じられます。
Daigo著『一瞬でYESを引き出す心理戦略』より抜粋
英語を教える上でも、相手が関心を持って聞いているかどうかを見抜くために相手をよく観察することが大切です。なぜなら、関心を持ってもらえないと伝えた内容がその人の頭に入っていかないからです。
つまり、
相手がつまらない感じているようなら、切り口を変える
必要があります。
ついつい教える内容自体に意識が行きがちですが、人によって同じ教え方をしても響く人と響かない人がいます。
なので、教える相手によって
- 具体例をたくさん挙げる
- 文の構造を詳しく説明する
- 文法を詳しく解説する
等、どのアプローチがいいのか相手を観察して見極め、柔軟に対応していく必要があります。
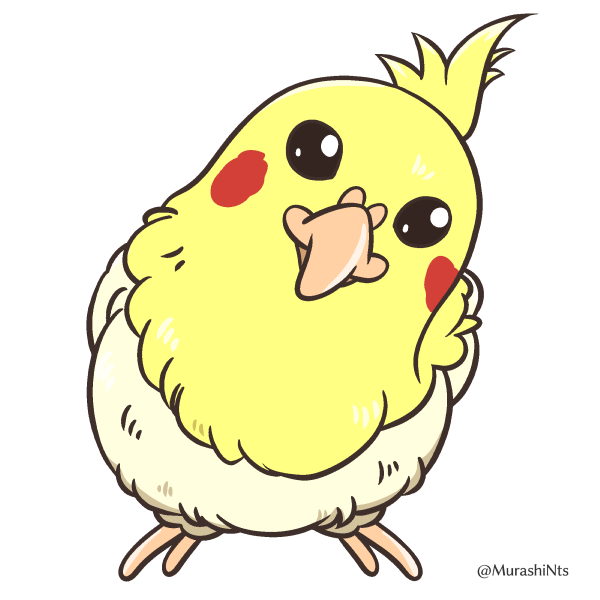
自分の言うことに関心を持ってもらいたかったら、まず自分が相手に関心を持たなきゃ。
無口な人ほど、実は話したがっている
これについては、自分がどちらかというと「無口な人」の立場なので納得できました。自分から話しかけるのは苦手でも、人と話すこと自体は嫌いじゃなかったりするんですよね。
本書では、
人間は基本的に自分のことを見てもらいたい、話しかけてもらいたい、わかってもらいたいという欲求を持っています。これは誰にも必ずある根源的な欲求です。
それでいながら、無口であまりしゃべらない人というのは、どんな話をすればいいのかわからないか、もしくは警戒心や恐怖心があってしゃべれない、だいたいがこのどちらかでしょう。人と会話するのが「嫌い」なのではなく「本当は話したいけれど話せない」人なのです。
Daigo著『一瞬でYESを引き出す心理戦略』より抜粋
と書かれています。
教える立場として考えるなら、会話が弾む人とばかり話していてはだめということですね。
質問すると黙り込んでしまったり、自分から質問はほとんどしてこない生徒さんもいるのですが、相手の能力の向上を望むなら、「無口な人」にもめげずに働きかけていく必要があります。
自分から質問できる人はそのままでも良いかもしれませんが、あまり喋らない人は教えた内容を理解しているのかしていないのかが分かりにくいですからね。
実際にあまり喋らない人ほど話を振るようにしていたところ、その人の授業に対する食いつき方が変わってきたと感じています。
終わりに
今回は英語を教える立場として人を動かす心理について学んだことを書きました。
今回ご紹介した本は、教える立場にいる人はもちろん、人に関心を持ってもらう必要がある人にとっても学ぶところが多いと思います。
気になった方は一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
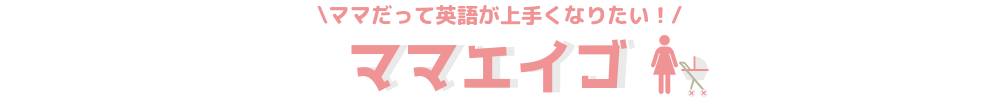


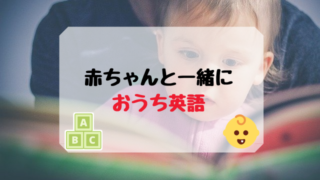

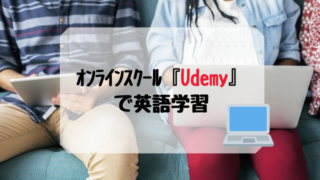

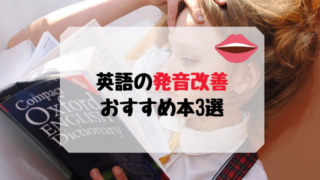
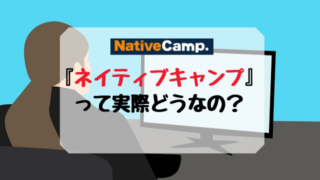

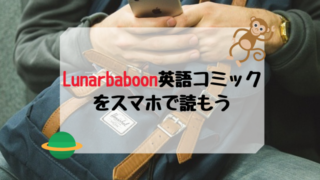

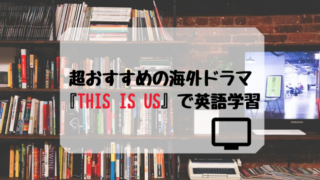






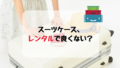
コメント